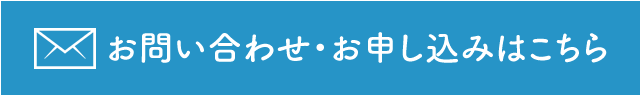腰痛予防労働衛生教育(作業従事者用)の受講が必要です
|
腰痛は、休業4日以上の業務上疾病の6割、業務上の負傷に起因する疾病の8割近くを占める労働災害となっています。腰痛を予防することは労働衛生上の大きな課題となっています。 厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策の推進について」を公表し、関係事業場に周知・普及を推進しています。 職場における腰痛の発生を予防するためには、労働衛生教育を実施することからはじめ、作業管理、作業環境管理、健康管理を適切に行い、腰痛発生の要因の排除と軽減を図る事が大切です。 事業者は、労働安全衛生法第60条の2に基づき、腰痛のリスクが高い業務に就かせる労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。 本教育は、製造業や建設業における重量物取り扱い作業をはじめ、立ち作業、座り作業、長時間の車両運転作業など腰部に著しい負担のかかる作業従事者に対して実施いたします。 |
 |
腰痛予防労働衛生教育の法的根拠
|
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。。 |
|
●職場における腰痛予防対策の推進について(基発0618第1号)【抜粋】 本指針は、このような腰痛予防対策に求められる特性を踏まえ、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入しつつ、労働者の健康保持増進の対策を含め、腰痛予防対策の基本的な進め方について具体的に示すものである。 |
|
●職場における腰痛予防対策に係る労働衛生教育の推進について(基発第136号)【抜粋】 |
腰痛予防労働衛生教育の受講が必要である
 |
腰痛とは、腰の部分を主とした痛みやはりの総称を指し、日本人口の約8割の方が人生において腰痛を経験しているというデータがあります。 腰痛には、椎間板ヘルニアなど原因が特定できる「特異的腰痛」と原因が特定できない「非特異的腰痛」がありますが、腰痛のほとんどは、非特異的腰痛によるものが大半を占め、原因の特定が難しいとされています。 そのため、作業において未然に予防できることを学び予防対策はもちろん、健康の促進を図ることを職場に取り込み、実施していくことが大切です。 「腰痛予防労働衛生教育(作業従事者用)」を受講し、正しい知識のもとで正しい作業をおこないましょう。 |
講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて
以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。