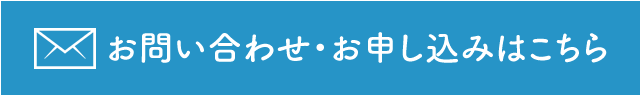熱中症予防労働衛生教育の受講が必要です
|
熱中症を発症しやすい職場の条件として、環境要因・作業要員・衣服要因・身体要因が挙げられます。熱中症は、正しい知識を習得し、正しい行動で防ぐことが可能です。 事業者は、高温多湿作業場所における作業を管理する者に対し、「熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)」を実施することが定められています。 厚生労働省通達により、2025年6月1日からは、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務づけています。WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業においては、罰則規定(懲役6か月以下または罰金50万円以下)が適用されます。
|
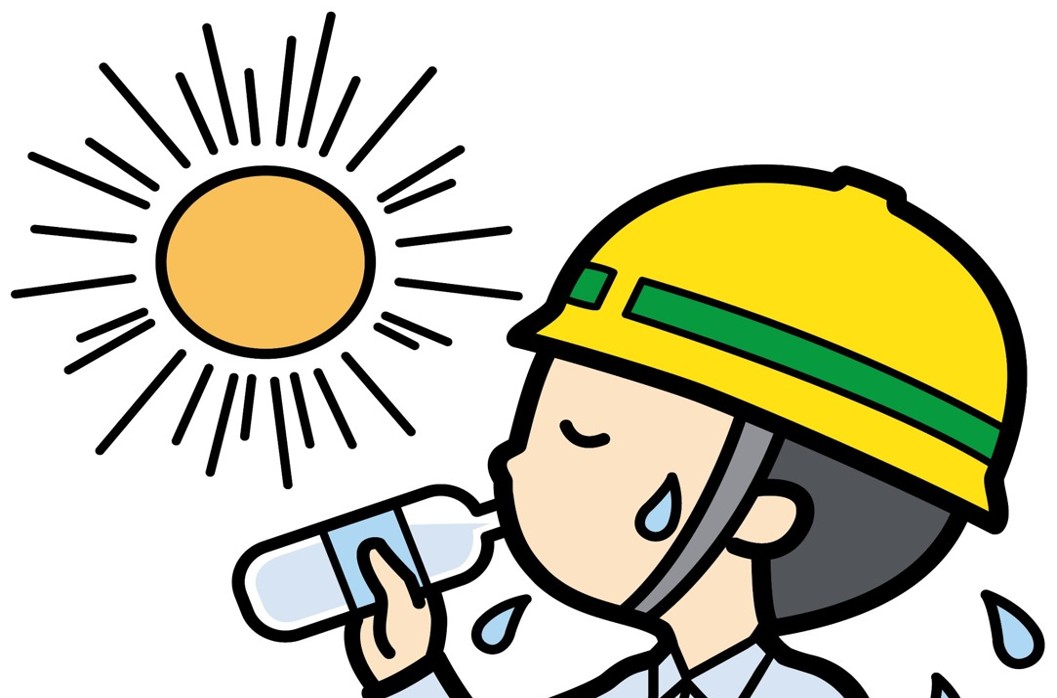 |
熱中症予防労働衛生教育の法的根拠
|
●労働安全衛生法第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
|
●労働安全衛生法第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 |
|
●労働安全衛生法第27条 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
|
●労働安全衛生法第60条の2 1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
|
●労働安全衛生法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。 |
|
●労働安全衛生規則第第606条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。 |
|
●労働安全衛生規則第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。 |
|
●労働安全衛生規則第第614条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 |
|
●労働安全衛生規則第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 |
|
●職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0420第3号) 【抜粋】 4 労働衛生教育 |
|
●令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 【抜粋】 1 趣旨 昨年までの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」においても、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んできた。 また、死亡者数は、建設業、製造業及び運送業の順に多く、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施を確認出来なかった。 また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もあった。 |
|
●第 14 次労働災害防止計画 イ アウトカム指標 4 重点事項ごとの具体的取組 (8)化学物質等による健康障害防止対策の推進 (イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと |
|
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労省発基安0312第1号) |
熱中症予防労働衛生教育の受講が必要である
 |
熱中症は、正しい知識の基で、正しい行動をおこなうことによって未然に防ぐことが可能です。 2025年6月1日(令和7年6月1日)より、熱中症の重篤化による労働災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、状況に応じて迅速かつ適切に対処することが可能になるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制の整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者の周知」が義務づけられます。 WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業においては、罰則規定(懲役6か月以下または罰金50万円以下)も導入されます。 |
講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて
以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。