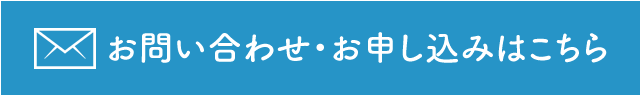騒音作業従事者労働衛生教育の受講が必要です
|
近年、騒音性難聴による新規労災認定者数は、年間300人程度で推移しており、騒音作業下において、長時間騒音作業に従事し続けると騒音性難聴を引き起こすリスクが懸念されます。 騒音性難聴を引き起こすと、現代の医学では治癒することが不可能といわれています。 騒音障害防止対策を適切におこなうには、正しい知識のもとで、正しい作業をおこなうことです。 事業者は、常時騒音作業に従事させようとする労働者に対し、「騒音作業従事者労働衛生教育」を実施するよう定められています。 「騒音作業従事者労働衛生教育」では、「騒音の人体におよぼす影響」、「聴覚保護具の使用の方法」について学んでいただきます。 |
 |
騒音作業従事者労働衛生教育の法的根拠
|
●労働安全衛生法第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
|
●労働安全衛生規則第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 |
|
●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2号) 1 目的 3 事業者の責務 別表第1又は別表第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする。 9 労働衛生教育 |
|
●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2 号) 別表1 (1)鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場 (2)ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場 |
| ●騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月20日付け基発第0420第2 号) 別表2
(1)インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場 (2)ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場 |
騒音作業従事者労働衛生教育の受講が必要である
 |
騒音作業場所で何の対策も講じずに作業に従事し続けると、多かれ早かれ騒音性難聴になります。 騒音性難聴は現代の医学では回復見込みが期待できない疾病のため、一度発症すると治癒することなく、一生付き合いしていかなければなりません。 騒音障害防止対策を講じることは事業者の責務でありますが、そこで作業に従事する作業者は正しい知識のもとで正しい作業をおこなうことが大切です。 管理者は「現場を守る・作業者を守る」、作業者は「自分のからだは自分で守る」ために、事業者は「騒音作業従事者労働衛生教育」を実施し、職場の騒音対策に取り組んでいくことで、安全・安心な職場を築いていきましょう。 |
講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて
以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。